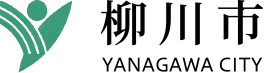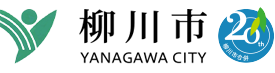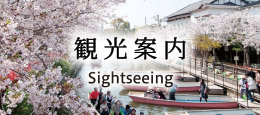家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
令和6年10月分より児童手当の制度が変わります。詳しくはこちら(内部リンク)をご覧ください。
※下記の内容も、制度改正後のものとなっております。
児童手当を受けられる人
日本国内に住所があり、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している人に支給されます。
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合を除く)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給
手当の月額
| 児童の年齢 | 児童手当月額(児童1人あたり) | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
|
3歳未満 |
1万5,000円 |
3万円 |
| 3歳~高校生年代 | 1万円 | |
※「第3子以降」については、下記をご参照ください。
「第3子以降」の算定基準
「第3子以降」とは、児童手当受給者が監護・養育をしている児童のうち、大学生年代以下の児童等を上から数えて3人目以降の児童が該当します。
※「大学生年代」…22歳到達後最初の3月31日までの子
大学生年代については、就職し収入がある場合でも、また別居している場合でも算定に入れることができる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
大学生年代を算定に含める基準について
1. 同居し、日常生活の世話・必要な保護をしている。
または、別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である。
2. 生計費の負担をしており、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない。
上記2点を満たしていれば、算定に入れることができます。
手当の支払
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回、それぞれの前月分までが支払われます。
支払日は各月とも10日(ただし、支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日)
手当の年間支払スケジュールはこちら(内部リンク)
所得制限限度額
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度改正により、所得制限が撤廃されました。
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※父母で児童を養育している場合は、これまでどおり原則所得の高いほうを受給者とします。
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は窓口に請求の手続きをしてください。
原則として、請求をした日の属する月の翌月分から支給されますが、転入または出産等やむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証または資格確認書のコピー(マイナ保険証のみの場合は、添付不要)
- その他必要な書類
詳しくは、児童手当を受給するにはどうしたらいいですか(内部リンク)をご覧ください。
いろいろな届出
現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
<現況届の提出が必要な方>
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が柳川市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 第3子以降加算対象の大学生年代で、職業等が「学生」以外(就職など)の子がいる方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、柳川市から提出の案内があった方
その他の届出
- 2人目以降の児童が生まれたとき
- 市外へ転出するとき
- 児童と別居するようになったとき
- 第3子以降加算対象の大学生年代の子の状況が変わったとき(子の就職、退学、婚姻、転居などにより、受給者が経済的負担をしなくなったなど)
- 公務員になったとき など
上記のような場合は、窓口で手続きが必要です。
詳しくは、児童手当の届出内容に変更があったときの手続きを教えてください(内部リンク)をご覧ください。
関連リンク
- 申請書ダウンロード(内部リンク)
- 児童手当を受給するにはどうしたらいいですか (内部リンク)
- 児童手当の振込口座を変更するにはどうしたらいいですか(内部リンク)
- 児童手当の届出内容に変更があったときの手続きを教えてください(内部リンク)
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者