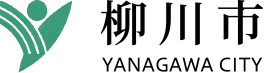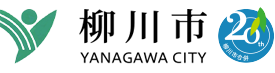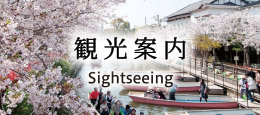この制度は、75歳以上の人と一定の障害の認定を受けた65歳以上の人を対象とした、独立した医療制度です。後期高齢者医療の被保険者(対象者)になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(サラリーマンの健康保険)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
対象者
◆75歳以上の人(強制加入)
◆65歳以上75歳未満で一定の障害のある人(任意加入)
「一定の障害」のある方とは
1.国民年金法などによる障害基礎年金1級または2級の方
2.身体障害者手帳の1級、2級、3級の方または4級で
(1)音声機能の障害
(2)言語機能の障害
(3)そしゃく機能の障害
(4)下肢障害の1号・3号・4号のいずれかに該当する人
3.療育手帳「A」の認定を受けている人
4.精神障害者障害程度等級1級・2級の人などです。
8月から資格確認書が新しくなります。
現在の被保険者証及び資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までです。
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
今回は、8月1日から使用できる「資格確認書」(紫色)を、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、マイナ保険証の有無に関わらず郵送します。有効期限は、令和8年7月31日までの1年間となっており、7月下旬までにお届けします。
マイナ保険証での受付が難しい場合は、今回お送りする新しい資格確認書で、8月1日以降もこれまで通りの医療を受けることができます。
7月31日までに新しい資格確認書が届かない場合は、市健康づくり課医療年金係(柳川庁舎1階16番窓口)へお問い合わせください。
◆資格確認書に限度額の適用区分が併記できます。
被保険者証同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、新たに発行されなくなり、資格確認書に限度額の適用区分を併記する仕組みとなりました。
令和6年度中に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていた方、既に限度額の適用区分が併記された資格確認書をお持ちの方へは限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付します。
※資格確認書に限度額の適用区分の併記を希望される場合は市窓口への申請が必要です。
申請受付窓口 柳川庁舎1階16番窓口 健康づくり課医療年金係、又は大和庁舎、三橋庁舎1階市民サービス課
◆資格確認書の自己負担割合をご確認ください
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割又は3割です。
毎年、前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。
同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上(※)である場合には、3割となります。
ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1又は2に該当する場合は、市窓口へ申請すれば、自己負担割合は1割または2割となります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の1又は2に該当)
(1) 本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満
※住民税課税所得が145万円以上であっても、前年の12月31日現在において、被保険者が世帯主であり、かつ、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から、16歳未満は1人当たり33万円、16歳以上19歳未満は1人当たり12万円をそれぞれ控除した後の額で判定します。(この場合の届出は不要です)なお、住民税課税所得が28万以上145万未満の2割負担の方にも同様の判定基準が適用されます。
※住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額で判定します。(届出は不要です)
◆マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
《マイナ保険証のメリット》
●お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる
●手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除される
●救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
問い合わせ先
市健康づくり課医療年金係 電話 0944-77-8503(直通)
又は 福岡県後期高齢者医療広域連合 電話 092-651-3111
マイナ保険証の利用解除
後期高齢者医療保険に加入中でマイナ保険証をご利用されている方のうち、マイナ保険証の利用登録を解除したい方は、市の後期高齢者医療担当窓口へご申請してください。
保険料のしくみ
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費(国、県、市町村)で約5割を、現役世代の保険料で約4割を、残り約1割を高齢者のみなさんからの保険料で負担します。
後期高齢者医療制度の仕組みの図
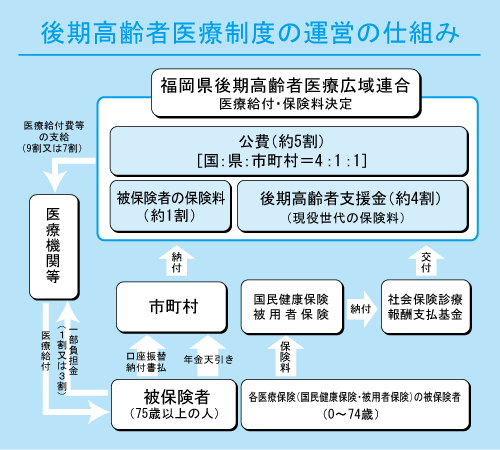
保険料の決まり方
保険料は、個人単位で計算され、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。ただし、所得や制度加入直前の医療保険の加入状況によって、保険料が軽減されます。
均等割の金額と所得割の率については、広域連合で定められていますので、福岡県内では均一になっており、2年毎に見直しを行います。
保険料額の決定内容は、毎年7月に通知します。
【令和7年度の保険料計算式】
保険料(年額)=被保険者均等割額+所得割額
=60,004円+(総所得金額等-基礎控除額)×11.83%(所得割率)
備考:保険料の最高限度額は80万円(年額)です。
備考:総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、各種控除前の金額です。
備考:所得により、保険料が軽減されます。
備考:制度加入日の前日において、被用者保険の被扶養者であった人は、特例措置として均等割額の5割が軽減されます。所得割額はかかりません。
詳しくは、下記をご覧ください。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は納付書などで納めます(普通徴収)。
ただし、介護保険と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える場合など年金からの天引きとならない場合があります。
健康診査の実施
福岡県後期高齢者医療広域連合は、健康診査を実施します。
- 対象者
後期高齢者医療の被保険者
- 期間
4月下旬から翌年3月31日(年1回)
- 受診票の送付時期
4月末現在で被保険者の人は4月下旬に、5月以降に被保険者になる方は被保険者になる月の10日ごろに送付します。
- 受診方法
医療機関に個別に予約し、受診票、被保険者証(または資格確認書もしくは保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、自己負担金500円を持参のうえ、受診ください。
歯科健診の実施
福岡県後期高齢者医療広域連合は、歯科健診を実施します。
- 対象者
本年度に76歳~80歳になられる後期高齢者医療の被保険者(ただし、長期入院及び一部施設入所者の方は除く)
令和5年度から対象者が上記の方になります。
- 期間
6月~12月(年1回)
- 受診券の送付時期
5月下旬に送付します。
- 受診方法
歯科医院に個別に予約し、受診券、被保険者証(または資格確認書もしくは保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、自己負担金300円を持参のうえ、受診ください。
なお、福岡県後期高齢者医療広域連合が指定している歯科医院での受診となります。
受診できる歯科医院の一覧につきましては、受診券と一緒に送付します。
福岡県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンターの設置
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)等に伴う制度改正の趣旨や改正内容等について、国民の皆様に丁寧に説明しご理解いただくため、被保険者等からの問い合わせに対応するコールセンターを、国において設置されるものです。
【設置期間】令和7年7月1日(火)~令和8年3月31日(火)※日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応期間】午前9時~午後6時
【電話番号】0120-117-571(フリーダイヤル)
※なお、マイナ保険証や資格確認書に係る問い合わせについては、引き続きマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にて承ります。
令和7年度歯科検診のお知らせ ~受診期間は、令和7年12月まで~
後期高齢者医療広域連合では、下記の被保険者を対象に、後期高齢者の口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯科検診を実施しています。令和7年度の受診期限は令和7年12月までです。まだ受診されていない方は、お早めにご予約の上、受診券をもって受診しましょう。受診券は5月下旬に発送しています。受診券をお持ちでない方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
〇受診対象者
昭和20年4月1日から昭和25年3月31日生まれの、今年度76歳~80歳になられる方。(※長期入院及び一部の施設入所者の方は除く)
〇受診期間
令和7年6月から令和7年12月まで(歯科医院の休診日を除く)
〇受診券の発送時期
令和7年5月下旬
〇受診の方法
受診券に同封している実施歯科医院に予約のうえ受診してください。
〇受診時に持っていくもの
・受診券(記入して実施歯科医院へお持ちください)
・マイナ保険証または資格確認書
・受診時の自己負担金300円(通常約4,600円の検査を300円で受診することができます。)
■問い合わせ先
福岡県後期高齢者医療広域連合 お問い合わせセンター
〒812-0044
福岡市博多区千代四丁目1番27号(福岡県自治会館5階)
電話:092-651-3111・FAX:092-651-3901
年に一度は健康診査を受けましょう
福岡県後期高齢者医療制度の被保険者を対象に生活習慣病の重症化やフレイルの予防等を目的とした健康診査を実施しています。
通常9,000円の検査を500円で受診することができますので、まだ受診されていない方は、お早めにご予約の上、この機会に健康診査を受けましょう。
〇受診対象者
全ての被保険者の方
※長期入院及び特別養護老人ホーム等の施設入所者の方は対象外。
〇受診期間
令和7年4月から令和8年3月31日まで(検診実施機関の休診日を除く)
〇受診券の発送時期
令和7年4月末現在で被保険者の方には4月中旬~5月上旬に送付
令和7年5月以降に被保険者になる方(75歳到達等)には、誕生月の10日頃又は資格取得の翌月以降の10日頃に送付
〇受診の方法
受診票が届いてから個別検診(医療機関での)健康診査を申し込んでください。
〇受診時に持っていくもの
受診票、マイナンバーカード又は資格確認書、自己負担金500円
〇問い合わせ先
福岡県後期高齢者医療広域連合 お問い合わせセンター
〒812-0044
福岡市博多区千代四丁目1番27号(福岡県自治会館5階)
電話:092-651-3111 FAX:092-651-3901
福岡県後期高齢者医療広域連合リンク
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者