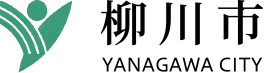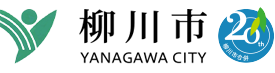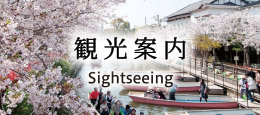老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。
「受給資格期間」とは、次の期間の合計をいいます。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の免除を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険や共済組合などの加入期間
- 第3号被保険者であった期間
※平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
合算対象期間
合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されますが、年金額の算定には反映されません。
主なものは次のとおりです。
- 厚生(共済)年金に加入している人の配偶者で昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間
- 平成3年3月以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以後、厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間
- 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間に国外に在住していた期間等
年金額
令和7年度(満額) 831,700円(月額69,308円)
20歳から60歳まで40年間すべて保険料を納めると、満額の老齢基礎年金を受給できます。
免除や未納期間があると減額されます。
繰上げ支給・繰下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて請求できます。この場合、その時の年齢に応じて年金額が減額され、65歳以後も減額されたままです。反対に、66歳までに請求しなかった人は、申出により66歳以後に繰下げて増額された年金を受給することができます。
繰上げ支給の注意事項
※一度請求すると取消はできません。
※請求時年齢の支給率となり、請求した月の翌月分から支給されます。
※減額率は受給者の生涯を通じて変更が認められません。
※付加年金も減額支給となります。
※事後重症などによる障害基礎年金は受けられません。
※寡婦年金は受けられません。
※遺族厚生(共済)年金を受給すると65歳までの間支給停止されます。
※国民年金に任意加入することはできません。
減額率= 0.5%×繰上げ請求月から65歳になる前月までの月数(昭和37年4月1日以前生まれの方)
減額率= 0.4%×繰上げ請求月から65歳になる前月までの月数(昭和37年4月2日以降生まれの方)
増額率= 0.7%×65歳になった月から繰下げ申出月の前月までの月数
障害基礎年金
国民年金加入中などに、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害になったときや、20歳前に同程度の障害の状態になったときに支給されます。
初診日要件
- 国民年金加入期間中に初診日があること。
- 以前に被保険者だった人で日本に住所があり、60歳以上65歳未満の期間に初診日があること(「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日。)。
納付要件
初診日のある月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除承認期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
このため、保険料の滞納があると年金が支給されないことがあります。
- 初診日が令和8年4月1日前にあり初診日において65歳未満の場合は、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても支給されます。
- 初診日が平成3年4月30日までにあるときは、初診日がある月の前々月ではなく、初診日のある月前の直近の基準月(1、4、7、10月)の前月までの被保険者期間が対象です。
障害の程度の要件
障害認定日に政令で定められている障害等級の1級または2級の障害の状態になっていること。
- 政令で定められている障害等級の1級、2級は、身体障害者手帳の等級とは異なる。(「障害認定日」とは、初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日。)
年金額(令和7年度)
- 障害等級1級:年金額1,039,625円(月額86,635円)
- 障害等級2級:年金額831,700円(月額69,308円)
障害基礎年金を受給する人に生計を維持されている18歳になった年度末までの子、または20歳未満で障害等級の1級、2級の障害がある子がいるときは次の額が加算されます。
子の加算額(令和7年度)
- 1人目・2人目の子:1人につき239,300円
- 3人目以降の子:1人につき79,800円
20歳以前の障害
20歳前に初診日があり1級、2級に該当している場合は、20歳(障害認定日が20歳を超えるときは障害認定日)の翌月から支給されます。
ただし、本人の所得などによる支給の制限があります。
事後重症による年金
障害認定日に1級、2級の障害の状態になかった人が、その後65歳になる前に障害が悪化し、1級、2級に該当するようになれば支給されます。ただし、この場合65歳になるまでに請求しなければなりません。
はじめて2級による年金
すでに障害のある人がさらに別の障害が起こったときに、すでにある障害と新しい障害を併せた障害の程度が、65歳になるまでに初めて2級以上に該当するようになったときは障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の人、老齢基礎年金の受給権者、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます(子のない配偶者には支給されません)。
支給要件
死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除承認期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たしていれば支給されます。
このため、保険料の滞納があると年金が支給されないことがあります。
受けられる人
死亡した人によって生計を維持されていた次の人に支給されます。
- 18歳になった年度末までの子または20歳未満で障害等級の1、2級の障害の状態の子と生計を同一にしている配偶者。
- 18歳になった年度末までの子または20歳未満で障害等級の1、2級の障害の状態の子。
年金額
- 子のある配偶者が受け取るとき
831,700円+(子の加算額)
- 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
831,700円+(2人目以降の子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額・・・・各239,300円
3人目以降の子の加算額・・・・・・・・各 79,800円
国民年金の独自給付
付加年金
国民年金の定額保険料のほかに、付加保険料を納めた人に次の金額が老齢基礎年金に毎年加算して支給されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
※国民年金基金加入中の人は、付加年金を納付することはできません。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除承認期間とを合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなったときに、その夫に生計を維持され、10年以上の婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金額=夫の老齢基礎年金額×3/4(第1号被保険者の期間に相当する老齢基礎年金額)
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
付加保険料納付済期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。
保険料納付済期間と年金額
- 3年以上15年未満:120,000円
- 15年以上20年未満:145,000円
- 20年以上25年未満:170,000円
- 25年以上30年未満:220,000円
- 30年以上35年未満:270,000円
- 35年以上:320,000円
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要で、支給要件は下記のとおりです。
支給要件
〇65歳以上で老齢基礎年金を受給している方のうち、以下の要件を全て満たす方
・請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税である
・昭和31年4月1日以前生まれの方・・・年金収入額とその他の所得額の合計が906,700円以下である
・昭和31年4月2日以後生まれの方・・・年金収入額とその他の所得額の合計が909,000円以下である
〇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方のうち、以下の要件を満たす方
・前年の所得額※1が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
請求の手続き方法
〇新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
・対象となる方には、日本年金機構より9月初旬頃から順次、請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、日本年金機構へ提出してください。(令和8年1月5日までに請求手続きが完了すると、令和7年10月分から遡って受け取ることが出来ます。)
※すでに受給中の方は手続き不要です。
〇年金を受給し始める方
・年金の請求手続きと併せて請求手続きを行ってください。(手続きが出来るのは、65歳になる誕生日の前日以降になります。)
手続き後の流れ
審査結果の通知が日本年金機構から到着
↓
支払い月の上旬に振込通知書が日本年金機構から到着
↓
通知書に記載がある給付額が年金とは別途支給
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者