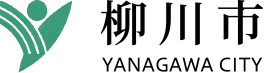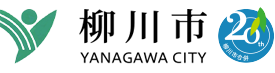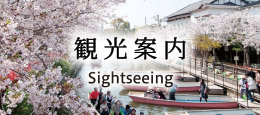ページ内目次
国民健康保険税
国民健康保険税納税通知を送ります
令和7年6月末までに国民健康保険に加入の世帯に対して、令和7年度国民健康保険税納税通知を7月中旬に送付します。
第1期(7月送付分)の納付書も併せて送付しますので、令和7年7月31日(木曜日)までの納付をお願いします。
また、月々の支払いを忘れないためにも、口座振替が便利です。口座振替をご希望の方は、口座振替依頼書をお渡ししますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
令和7年度国民健康保険税
|
所得割 |
均等割 |
平等割 |
最高限度額 |
|
|
(1)医療保険分 |
8.50% |
29,000円 |
31,000円 |
660,000円 |
|
(2)後期高齢者支援金分 |
2.57% |
9,067円 |
9,711円 |
260,000円 |
|
(3)介護保険分 |
2.38% |
10,789円 |
8,446円 |
170,000円 |
40歳未満の人
(1)医療保険分と(2)後期高齢者支援金分の国民健康保険税を納めます。
40歳から64歳までの人
(1)医療保険分と(2)後期高齢者支援金分と(3)介護保険分を合わせて、一つの国民健康保険税として一緒に納めます。
65歳から74歳までの人
(1)医療保険分と(2)後期高齢者支援金分の国民健康保険税を納め、介護保険料は別に納めます。
なお、世帯内の国民健康保険加入者がすべて65歳以上の場合、国民健康保険税は原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。
国民健康保険税の決め方
令和7年度国民健康保険税は、次のような方法で計算されます。
- 所得割額は、世帯の所得に応じて計算(前年の所得から43万円(基礎控除)を差し引いた額に税率を乗じて計算)
- 均等割額は、世帯の加入者数に応じて計算
- 平等割額は、1世帯につきいくらと計算
(1)医療保険分
所得割額(税率8.5%)+均等割額(29,000円×人数)+平等割額(1世帯につき31,000円)
<1年間の保険税額の限度額66万円>
(2)後期高齢者支援金分
所得割額(税率2.57%)+均等割額(9,067円×人数)+平等割額(1世帯につき9,711円)
<1年間の保険税額の限度額26万円>
(3)介護保険分
所得割額(税率2.38%)+均等割額(10,789円×人数)+平等割額(1世帯につき8,446円)
<1年間の保険税額の限度額17万円>
国民健康保険税の決め方(例)
年間所得が260万円の4人世帯でその世帯に40歳から64歳までの人が1人いる場合(その人の所得が給与所得で260万円の場合)
1年間の保険税額は、
(1)医療保険分331,400円+(2)後期高齢者支援金分101,700円+(3)介護保険分70,800円=503,900円
(1)医療保険分
年間の医療保険税額は33万1400円(100円未満切捨)
所得割額(260万円-43万円<基礎控除>)×8.5%=184,450円
均等割額29,000円×4人=116,000円
平等割額31,000円×1世帯=31,000円
(2)後期高齢者支援金分
年間の後期高齢者支援金税額は10万1700円(100円未満切捨)
所得割額(260万円-43万円<基礎控除>)×2.57%=55,769円
均等割額9,067円×4人=36,268円
平等割額9,711円×1世帯=9,711円
(3)介護保険分
年間の介護保険料は7万800円(100円未満切捨)
所得割額(260万円-43万円<基礎控除>)×2.38%=51,646円
均等割額10,789円×1人=10,789円
平等割額8,446円×1世帯=8,446円
納付確認書(確定申告用)を送ります
毎年1月中旬に、国民健康保険税の年間納付額を記載した納付確認書(確定申告用)をお送りしています。
会社での年末調整などに使うために、事前に必要な人は窓口または電話で申し出てください。
窓口お越しの際には本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証などを持参してください。
世帯内の被保険者毎の明細が必要な場合は、作成に時間がかかりますので、受付して2~3日後のお渡しになります。
なお、事前交付を希望された世帯には、1月中旬の一斉送付時にはお送りしません。
12月~1月中旬の一斉発送までは、下記申請フォームからも受け付けています。
◇納付確認書(確定申告用)申請フォーム(ふくおか電子申請サービス)
国民健康保険税の軽減措置及び減免制度について
出産(予定)者の産前産後期間に係る所得割・均等割が軽減されます。
令和6年1月より、国民健康保険に加入している出産した人または出産予定の人の、産前産後期間について所得割・均等割が軽減されます。
※軽減を受けるには届け出が必要です。 出産予定日の6か月前から届け出できます。
【対象者】
・出産した人または出産予定の人で、対象期間中に国民健康保険に加入している人
出産には、妊娠85日以上の分娩であれば、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
※なお、対象期間に制度開始の令和6年1月以降の月が含まれる令和5年11月以降出産(予定)の人が対象です。
【対象期間】
・出産(予定)月の前月から4か月(多胎妊娠は出産(予定)月の3か月前から6か月)のうち、国民健康保険に加入している期間
※なお、制度開始の令和6年1月以降の期間が対象です。
【軽減内容】
・対象者の対象期間中の所得割、均等割について月単位で減額します。
・対象期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度で属する月分を減額します。
※ただし、国民健康保険税は同じ世帯の国保加入者分を合計し限度額の判定をするため、世帯員の保険税額によっては軽減が適用されていても限度額が世帯の保険税額になるため、軽減前と変わらない額となって実質減額にならない場合があります。
【届け出に必要なもの】
・出産日または出産予定日を確認できる書類
・単体妊娠・多胎妊娠の別が確認できる書類
(母子手帳など)
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減届出書(様式) (PDF 264KB)
未就学児に係る均等割が軽減されます
令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校に就学する年齢に満たない児童)に係る均等割額(一人当たりの金額)の5割が減額されます。
低所得者軽減が適用される世帯は、軽減後の額から5割軽減となります。この軽減措置は自動で適用されるので、手続は不要です。
|
低所得者軽減 |
均等割額 | 軽減適用後 |
|---|---|---|
|
軽減なし |
38,067円 |
19,033円 |
|
2割軽減 |
30,453円 |
15,226円 |
|
5割軽減 |
19,033円 |
9,516円 |
|
7割軽減 |
11,420円 |
5,710円 |
備考:国民健康保険税は、同じ世帯の被保険者分をまとめて100円単位で課税するため、実際の課税額は上記と異なる場合があります。
低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
軽減制度が適用されるかどうかは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員の所得により判定するため、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されません。会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合、誰かの被扶養者(扶養控除の対象)になっている場合を除いて、必ず4月15日までに所得の申告をお願いします。
※所得の申告書をもとに計算しますので、手続は不要です。
| 令和7年度 | |
| 7割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1) |
| 5割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1) |
| 2割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1) |
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)を受ける者
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置
解雇や倒産、雇い止めなどの非自発的失業者は、保険税の負担が軽減されます。
※軽減を受けるには、申請が必要です。
【対象者】
・失業し、次の雇用保険の失業等給付を受ける人(離職日の翌日において65歳未満であること)
・雇用保険の「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」
(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が、11・12・21・22・23・31・32・33・34)
【軽減される額と期間】
・前年の給与所得金額を、実際の金額の30/100とみなして算定します。
・期間は、離職の翌日から翌年度末までです。
【申請に必要なもの】
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・個人番号カード(ない場合は(1)運転免許証などの本人確認書類と(2)個人番号が確認できる書類)
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減申告書(様式) (PDF 127KB)
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減措置
【特定世帯】
これまで国保被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
特定世帯では、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後3年間は4分の1が軽減されます。 (世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
【旧被扶養者】
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等)の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の人を「旧被扶養者」といいます。
旧被扶養者は、所得割額がかかりません。また、均等割額は半額となります(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)。
さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額となります。(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となっている場合は該当しません。
国民健康保険税の減免制度
災害やその他の特別な事情が生じて保険税を納めることができなくなった場合は、お早めにご相談ください。
一定の基準に該当し、資産などを活用してもなお保険税の納付が困難な場合は、状況に応じて保険税が減額されることがあります。
国民健康保険税を滞納したとき・支払いに困ったとき
国民健康保険税(国保税)を滞納したとき
- 納期限を過ぎても納付されない場合、督促状が届きます。この場合、督促手数料100円が加算されます。 そのほか、納期限を過ぎると延滞金が加算されたり、滞納が続くと財産の差し押さえ(滞納処分)が行われる場合があります。
- 正当な理由なく1年以上国保税を滞納すると、通常の療養の給付等に代えて特別療養費の支給に変更されることになります。
- 特別療養費の支給に変更されると特別療養と記載した資格確認書を交付します。また、マイナ保険証も特別療養費の支給に変更されたことが医療機関等でわかるようになります。
- 特別療養費の支給に変更されると、医療費を一旦は全額負担していただくことになります。支払った医療費のうち自己負担分(2~3割)を除いた額は、領収書を添えて市役所窓口で特別療養費の支給申請をすると払い戻しますので、滞納している国保税に充てるようお願いします。
国保税の支払い(納付)に困ったとき
- 滞納をそのままにしておくと、督促手数料や延滞金が加算され滞納額が膨らみます。このような場合は、お早めに健康づくり課国民健康保険係(柳川庁舎)・市民サービス課(大和庁舎・三橋庁舎)または税務課収税対策係(柳川庁舎)にて納税相談を行ってください。
- 口座振替にすると、納付もれの心配がなくなりますのでぜひご利用ください。
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者