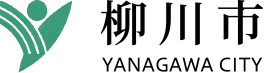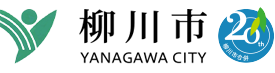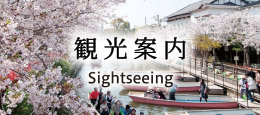並倉
明治24年(1891)年6月、山門郡三橋村字江曲で、小さな味噌製造所が操業を開始しました。青年起業家吉開治吉の手によって設立された吉開鶴味噌です。
明治34年(1901)、治吉は、味噌醸造業に専念することになり、この頃から鶴味噌は急速に業績を伸ばしていったようです。陸軍や三池鉱山の御用達にも指名されるようになり、日露戦争の頃になると製造所は昼夜となく操業するほどの忙しさでした。製造所で製産された米・麦・太白味噌は並倉の前で船に積まれ、堀割を巡り、やがて汽車や汽船に積み替えられて全国に配送されていきました。店舗の方も柳川だけではなく、久留米や佐世保そして大連にまで支店を構えるようになりました。
事業の拡大に伴い、製造場の拡張、倉庫の増築、新型機械の導入などを行いました。昔の写真では、敷地の中央に巨大な煙突が立てられていたことも窺えます。こうした施設は、言うなれば鶴味噌の興隆の証でもあるのです。堀割に面して建つレンガ造りの3棟並んだ美しい建物、通称「並倉」もこうした証の一つです。この建物は味噌の麹室として利用され、製麹と呼ばれる作業が行われていました。今日ではレンガ造りの外観を保全したまま、中は改装されて冷蔵・温蔵室として利用され、平成12年に国の登録文化財に指定されました。
※この文章は、柳川市史別編『新柳川明証図会』、柳川文化資料集成第4集『柳川の社寺建築1』の山本輝雄氏(前編集委員)、松岡高弘氏(編集委員)、内山一幸氏(調査研究員)の執筆部分を編集したものです。
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者