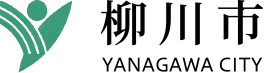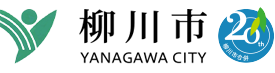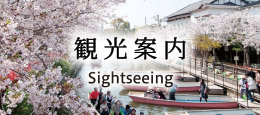柳川市内には、風流・どろつくどん・祇園・舟舞台囃子など、個性豊かな民俗芸能があり、各地域で継承活動を行っています。
この度、合併柳川市20周年を記念し、民俗芸能の保全と振興を図るため、市内の伝承団体が一堂に会し合併を祝って民俗芸能を開催します。大会当日は7つの市内民俗芸能を一挙に見ることができる貴重な機会に、多くの方にご観覧いただきました。
開催日・会場
開催日 :令和7年10月19日(日)
会 場:柳川市民文化会館 (柳川市上宮永町43番地1)
開場時間:13時
開演時間:13時30分
終演時間:17時
入場料 :無料
上演団体(出演順)
・今古賀風流 (今古賀風流保存会)
・沖端舟舞台囃子(沖端舟舞台囃子保存会)
・北徳益風流(北徳益風流保存会)
・子どもどろつくどん(どろつくどんを伝える会)
・柳川沖の石太鼓(三橋柳川沖の石太鼓振興会)
・日子山神社風流(日子山神社風流保存会)
・どろつくどん(柳川どろつくどん保存会) ※柳川市民文化会館西側駐車場で上演
今古賀風流
・今古賀風流は福岡県指定無形民俗文化財で、今古賀三島神社境内に竜神の石碑があり、この竜神に奉納する風流です。風流は、毎年10月の第2日曜日に行われます。行列の先頭は天狗二体で、これに鬼二体、猿面、おたふく、ひょっとこ、シャグマ(赤熊)、鉦が続く勇壮な行列です。
※当日は今古賀から風流を行いながら会場入りを行いました。
※10時30分に三島神社を出発し柳川警察署通りを進み、途中で奉納し12時頃に会場到着しました。
沖端舟舞台囃子
・沖端舟舞台囃子は毎年、5月の3日から5日に開催される沖端の水天宮大祭で、奉納される囃子です。囃子は、水天宮大祭のために作られる、舟舞台の上で演奏されます。舟舞台は、水天宮の前の掘割の水上に浮かべた6艘の船を繋ぎ合わせた、「三神丸」と名付けられている大きな船の上に舞台を作ります。舟舞台の形は、水天宮が合祀された文化・文政時代から引き継がれた形です。

北徳益風流
・北徳益風流は江戸時代享保の頃(約300年前)に始まったとされ、毎年10月の愛宕神社秋季祭礼の際に、五穀豊穣、無病息災を願い奉納されます。赤鬼・黄鬼が悪疫を払い、鉦・謡・太鼓とともに奉納される舞いは勇壮なものです。

子どもどろつくどん
・子どもどろつくどんは、どろつくどんの後継者を育成し、未来へ継承していくために発足しました。柳河小学校の4年生以上の希望する子ども達で組織しています。毎年6月から11月にかけて、毎週木曜日に練習しており、山車の上で踊る様子や笛・太鼓は、大人顔負けの「どろつくどん」です。
柳川沖の石太鼓
・柳川沖の石太鼓の由来は、立花宗茂が出陣の際に太鼓を打ち鳴らし、勇壮果敢な太鼓の音に鼓舞された立花軍は数々の武勲を立てたとされます。昭和50年、その出陣太鼓を復活させたのが現在の沖の石太鼓です。
日子山神社風流
・日子山神社風流は、福岡県指定無形民俗文化財です。江戸時代元和の頃(約400年前)、古賀村境を流れる沖端川に流れ着いた蓑を被った大臼を村童が拾い上げ、臼の中から燦然と輝く鏡を発見しました。不思議な出来事に喜び、鏡を神社に奉納するとともに、これを記念して喜びを風流として後世に伝えたのが始まりとされます。
どろつくどん
・どろつくどんは福岡県指定無形民俗文化財です。どろつくどんは、三柱神社の秋季大祭である「御賑会」の神幸行列の先頭を進む山鉾のことを「どろつくどん」と呼びます。どろつくどんの始まりは文政八年(1825)三柱神社造営の基礎工事(方言ではドウヅキ)が行われた際、旧柳河町の商人たちが無償奉仕でこれを手伝い、女衆が三味線と太鼓で興を添えました。しかし問屋街ではこれに加わらなかったため、不評を買ってしまいました。なんとか名誉を挽回しようと考えた問屋の北川新十郎、弥永久右衛門が江戸の神田明神に奉納されていた葛西囃子と京都の祇園山鉾を参考にお囃子と山車を作り、翌年の遷座式に披露して大好評を得たそうです。それ以降毎年、三柱神社のお祭りに奉納されるようになりました。山車は車の上に4本柱を立て幕を廻し、中央に種々の鉾を立てたもので、大太鼓、小太鼓、横笛、ドラ、鉦の囃子が乗ります。さらに山車の前に面を付けた舞方が乗り、囃子に合わせて素朴な舞を奉納します。
江戸時代には各町から山車が奉納されていましたが、現在は上町、蟹町、京町、保加町の4町に加え、有志で組織された飛龍会の5台が奉納されます。
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者