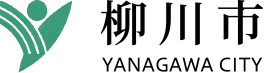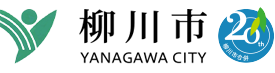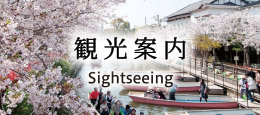知人の勧めで、熊本県玉名市にある「玉名牧場」を視察してきました。
玉名牧場は、自然の営みを大切にした酪農を行っている農場で、
柳川にも必ず参考になることがあるはずとにらんで訪問してきました。
結果的には、想像以上の大収穫でした!
玉名牧場の詳細を知りたい方はこちらからご覧ください。
玉名牧場ウェブサイト(外部サイトにリンク)

入り口で私たちを迎えてくれたアイちゃん。
牧場で最年長の彼女は15歳。
人間に換算すると80歳のおばあちゃんですが、まだ出産します!
玉名牧場の牛たちは多産で、それは食べ物に秘密があるとか。
通常の牧場では、3回ほど出産するだけだそうです。
アイちゃんはすでに13回!!
この時点ですでに玉名牧場のすごさが感じられます。

標高200mの山上に広がる広大な放牧地。
東京ドーム3個分の広さに、たった30頭しか飼育していません。
ぜいたく過ぎるように思えますが、自然の営みではこの広さが必要とのこと。
牛という生物が本来食べてきた牧草だけを与え、牛舎もありません。
だから、他の牧場の牛たちと比べると、骨張って見え、骨盤が大きく張り出しています。
しかし、空腹で気が立っているということはなく、非常に穏やかな気性の牛たち。
群れのボスである雄牛でさえも、初めて会う私たちに自由に触らせてくれます。

極めつけがこれ!
そうです。牛糞です。牛のうんこです。
うわっ! そんなもの素手で触って汚い!!
と思う方もいるでしょうが、これまったく臭くないんです。
(さすがにしたばかりのものは触れません。乾燥してからです)
手で割って、鼻に近づけて臭いをかぐと、ほのかに草の香りが!
良い餌を食べた牛は、こんなうんこをすることに驚くと同時に納得。
牛を人間に置き換えてみましょうか。
私たちの排泄物の臭いのもとは、つまりは自分の食べたものということ。
怖いなあと思いませんか?
実際、自分がヨーロッパに一ヶ月いたとき、体臭と排泄物の臭いがきつくなりました。
肉中心の食生活だったことが関係していたのでしょうね。
結局、自分の身体は、毎日食べるものが作ってくれているわけです。
こう考えると、いろいろなことが見えてきます。

牛に続いて、鶏にあいさつ。
だっこされても暴れない、つつかない鶏を見たことありますか?
牛と同様、鶏の気性も本当に穏やか。
この理由もやはり餌にありました。
放し飼いで、牧草など自然そのままの餌を食べると、こういう鶏に育つわけです。
一時期、子どもたちが「キレる」ということが話題になりましたね。
キレる理由はどのあたりにあるのか、この鶏の話はとても示唆的だと思います。
聞いた話なので信憑性の程は不明ですが、日本人の遺体は腐りにくいのだとか。
それは日頃から保存料や添加物の入った食べ物を摂取し続けているからだそうです。

この写真だけではなんだか分かりませんね。
これは、玉名牧場の堆肥です。
畜糞もまったく加えず、完全植物性の堆肥。
玉名牧場では、この堆肥のみを使用した無肥料栽培を行っています。
肥料を与えなくても十分に作物は生長するというお話。
連作障害もまったくないということでした。
つまりは土に窒素が多くなりすぎるために連作障害が起こるという説明で、
その意味では、有機農法という言葉も、すべてがいいものとは限らないわけですね。

たっぷりと時間をかけて説明してもらったあとでランチタイム。
牧場ご自慢のお肉をBBQでいただきました。
そして、ここでも玉名牧場マジック!!
かなりの量を食べた(普通、食べ放題で食べるくらいの量)のに、
まったく胃にもたれないのです。
脂のせいで気持ち悪くなることもまったくなし。
体温以下の温度で溶ける良質の脂のおかげということですが、
これは間違いなく我が身で体験して納得!!
ちなみに消化もよく、夕食時にはちゃんと空腹になりました。

牧場特製のチーズを使ったピザも美味でした!!
ここ玉名牧場では、採算性よりも自然の営みを優先した農場経営をしていますが、
こんなやり方できちんと経営できているのか不思議でした。
その答えは、当たり前の発想です。
つまりかかったコストに見合うだけの料金設定をして、
その金額で買ってくれる人と手をつなぐということ。
日本は食品にかけるお金が異常に低いと、私は感じています。
これは海外、特に欧米を旅行した人には分かることだと思います。
ちまたには格安食品があふれていますが、少し冷静になって考えてみましょう。
あなたが生産者だとして、その金額でその食品を生産できますか?
どうして地球の裏側からわざわざ来る食品が、国産のものより安いのですか?
TPPの問題や高齢化、後継者不足など、
日本の一次産業を取り巻く状況は非常に深刻になっています。
自分たちの国がこれまでたどってきた足跡を大切にし、
自分たちが食べてきたものをこれからも食べていきたいのであれば、
一次産業の人たちが、その労働に見合うだけの収入を得られる仕組みが不可欠です。
そのためには、まず消費者が賢くなることが必要です。
自分の身体は、自分が口にするものからできているという自覚をしっかり持つことです。
そして、きちんとした食品に対して、正当な対価を支払うことです。
同時に、生産者側にも努力が求められます。
採算性だけを考えて、健康に害のある食品を生産するのは論外ですが、
自分たちがどのようなやり方で生産しているのかという情報をきちんと発信しなければいけません。
そして、何よりも大切なのは、どういう思いでその作物を作っているのかという熱意。
言い換えれば、自分の作物に対する愛をしっかりと伝えること。
この2つがしっかりかみ合うことが、今後の日本の食を支えていくことになる。
玉名牧場に行って、このことを痛切に感じました。
毎日の食を大切にして、よりよい将来の日本をみんなで創っていきましょう!!
柳川市地域おこし協力隊
阿部昭彦
E mail 40207-nou-tok@city.yanagawa.lg.jp
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者