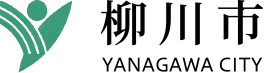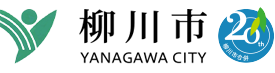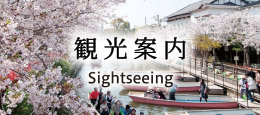みなさん、こんにちは。
地域おこし協力隊の阿部です。
先週、おいでん会のみなさんに同行させていただき、糸島半島の視察に行ってきました。
まず最初に訪れたのは「伊都国歴史博物館」です。
糸島半島にその昔存在した「伊都国」の歴史を中心に紹介しているこの博物館では、
朝鮮半島との結びつきの強さや、伊都国が日本に与えた影響力などを、
博物館職員の方に熱く語っていただきました。
福岡をはじめ、九州はその歴史的価値が非常に大きいことをあらためて実感しました。
柳川市には、このような古代遺跡はないようですが、その代わりに柳川独特の歴史文化があります。
江戸以前から続く干拓と堀割、そこに見られる人と水と米の関わりの深さ。
江戸時代の水争いの歴史および水利の工夫や、水の城と呼ばれる柳川城。
立花家や北原白秋に代表される数々の偉人の足跡。
日本最大の干満差と独特の生態系を誇る有明海の魅力。
うなぎの蒸籠蒸し、さげもんなどの柳川伝統文化。
こうした豊富な魅力を集約して見せられるしっかりとした施設があれば素晴らしいと思うのですが、いかがでしょうか。

昼食休憩をはさんで次に向かったのがJA糸島産直市場「伊都菜彩」。
テレビでもおすすめスポットとして紹介された通り、実に立派な施設でした。

野菜、花、魚介、畜産品などが、広いスペースいっぱいに展開されています。
そして、そのすべてが糸島産(と思われます)。
新鮮な野菜や魚介が、非常に安い値段で手に入ります。
中には割と高価な商品も並んでいますが、そのクオリティは高そうに見えました。
大勢のスタッフが休む暇なく、野菜の展示替えを忙しそうにしているので、
それも活気ある売り場の演出に役立っていたように思います。
糸島に住む知り合いの話では、最近は大型バスで観光客がやってくるようになったので、
地元の人は前よりも足が遠のいたということですが、それでも魅力あることに間違いありません。
一緒に行った方とお話ししたのですが、
柳川で道の駅を開いても、ここまでは品数が揃わないだろうとのこと。
確かに、花、魚介、畜産品の品数で考えたら、伊都菜彩ほど揃えるのは難しいでしょう。
しかし、数で勝負するのではなくオリジナリティで勝負すれば、いい勝負になります。
柳川ならではのものをしっかり売る道の駅はどうでしょうか?
柳川=ウナギというのは、すでにしっかりと確立されたブランドです。
それを中心に据えながら、それを目当てに来たお客さんが一緒にその他の野菜や商品を買う。
個人的にはもっと海苔をアピールしたいところですね。
今回、ニホンウナギが絶滅危惧種となったニュースからも分かるように、
ウナギは日本の食生活と非常に深く結びついています。
その心理をうまく使って宣伝できれば集客は期待できると思います。
しかも、有明海沿岸道路の開通や、ホークスファームの誘致など、
インフラの充実や観光客増加の期待もあります。
ぜひ実現してほしいことの一つですね。

最後に訪れたのは「峠の駅マッちゃん」。

平日の午後遅めの訪問という時間もあるのか、店内はちょっと寂しい感じです。
週末とか観光客が多いときはもっと賑わっているのでしょう。
ここは「ざる豆腐」を名物として強力にアピールしていました。
確かに出来たてでまだ温かいざる豆腐は美味しそうですね。

こんなワイルドな販売方法も「峠の駅」という名前には合っていますね。
確かに人気のある産直店というのはうなづけます。
三瀬峠の近くというアクセスの不便さがありながら、
しっかりと集客しているのは見事という他ありません。
今回の視察で考えたのは、消費者の興味というものは非常に移ろいやすいものだということ。
そうした消費者をしっかりと長くつかまえるにはどうすればよいのか。
目新しさや話題性だけで一時的に集客できても、それは長くは続かないでしょう。
やはり、その地域の日常をしっかりとうまくアピールすること以外に方法はありません。
柳川で長い時間、大切にしてきたものを提供できる場の創設が待ち遠しいところです。
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者