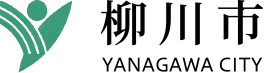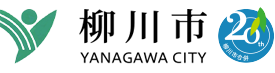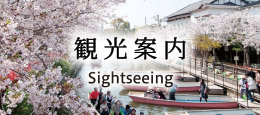みなさん、こんにちは。柳川市地域おこし協力隊員の阿部です。
先日、国産い草100%利用の花ゴザを生産する株式会社島松さんにお邪魔して、お話をうかがってきました。

以前、ここ筑後地方は、い草の一大生産地として全国でも有名でした。
ところが、生活様式の洋風化による畳の使用量減少と、安価な中国産い草の台頭により次第に衰退、
現在では少数の会社の努力によってかろうじて支えられている状況となっています。
聞くところによると、中国でのい草栽培は、日本から持ち込まれて始まったものとのこと。
実に皮肉な話ではありませんか。

国産い草と中国産い草の違いを島松さんにうかがうと、
「水の違いじゃないかな」という答えが返ってきました。
い草の断面を見ると、ストロー状の茎の中にスポンジのような組織が詰まっています。
硬水である中国で栽培されたい草は、このスポンジ部分が非常に貧弱で、そのために切れやすかったり、弾力が悪かったり、つやが出なかったりするのだそうです。
逆に、軟水の日本では、スポンジ部分が充実するため、丈夫で弾力があり、つやのよいい草となります。

このスポンジ部分には優れた吸着作用があるため、ホルムアルデヒドや二酸化窒素などの有害物質を浄化できるそうです。
また、吸放湿性も高く、室内の湿度が高いときには吸収、低いときには放出して、室内の湿度を適度に保つこともできます。
さらに、い草の香りには鎮静効果もあり、集中力が上がるため、勉強や仕事の効率もアップするらしいですよ。
い草ってすごいですね。

中国産の物はだいたい2年くらいで寿命を迎えますが、国産の物は10年は保つそうです。
使い始めてから5年も経つと、国産の物は光沢が出て来て、それがまた素晴らしい味わいになるらしいです。
色の出方にも大きな違いがあり、特に黒は、国産の物が美しく黒光りするのに対して、中国産の物は遠く及ばないそうです。

島松さんの工場に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、かなり年期の入った機械が忙しく働く姿です。
清潔でホコリ一つないという言葉とはまったく正反対(島松さん、すいません)の環境の中、実に滑らかに花ゴザを織り出す機械たち。
そのよどみない動きは単なる機械ではなく、生命を持った生き物に見え、しばらく見とれてしまいました。
そのことをお伝えすると
「本当に生き物なんですよ。たまに調子が悪くて、ちょっと止まってしまうこともあるのですが、少し経つとまた動き始めたりして、その様子は本当に人間を見ているみたいなんです」
と笑顔でおっしゃっていました。
いやあ、こういうシーンを子どもたちに見せたら、喜んでくれるんじゃないかな。

花ゴザの織り方は、機械の左右から染色したい草を入れ、それを縦糸によって織り上げていくという形式です。
織り方にもいろいろあるのですが、中でも「掛川織」という太い縦糸によって織り上げたものは、ボリューム感がありとても高級感のある織物になります。
1台の機械が1日に織れるのは10畳。
16台の機械が休みなく働いて、年間で約35000畳の花ゴザが生産されます。

生き物のような機械たちに囲まれて働く、素敵な人たちも紹介しましょう。
こちらは、機械に入れる前に、い草の長さをそろえる作業をしているところ。
無造作にい草をつかんでは、流れるような動きで切りそろえていきます。
い草を切るときの「ザバッ」という音が実に爽快!
思わず「私にもやらせてください!」と言ってしまいたくなります。
でも、この何気なく見える一連の動作こそが熟練の技。
素人がやったらこんなに美しくできません。

こちらは何をしているところか分かりますか?
丁寧に作ってはいても、ところどころ違う色のい草が混ざってしまうことがあります。
それを肉眼で見つけて、隣のい草を傷つけないように目打ちで抜き取っている作業です。
繊細で神経を使う仕事ですが、こちらも手慣れた手つきで、
あっという間に仕上げてしまいます。
華やかな技術ではないかもしれませんが、こうした人たちの経験と技術が、
美しい花ゴザを支えているのですね。

現在ではコンピュータによって、細かいデザインの花ゴザも織れるようになりました。
このタペストリーも、もちろんい草で織った花ゴザです。
定番のデザインもいいのですが、最近では企業のロゴや家紋など、オーダーメイドの花ゴザの注文も多いそうです。

現代的なデザインの花ゴザもあります。
こちらは「オーロラ」。
パッと見ただけでは普通のプリントしたようなラグマットに見えますね。

しかし、近寄ってみると、確かにい草を織って模様を出しています。

こちらのハート柄がかわいいものも同様です。

ハートの柄もさることながら、地紋の美しさが秀逸ですね。

夏の暑い夜には、このセットがおすすめ。
い草の枕と花ゴザのマット(布団の上に置いて使います)で、寝苦しい夜にもぐっすり寝られます。

今回ご紹介した株式会社島松さんは、国産い草100%の花ゴザにこだわって作り続けています。
現在では、い草を生産する農家が柳川には少ないため、原料のい草は熊本県八代のものが中心ですが、やはり国産い草の香りは、日本に暮らす私たちにとっては格別の物ですね。
もしこの記事を読んでご興味を覚えた方は、下記までお問い合わせください。
株式会社島松
〒832-0002 福岡県柳川市高島1912
TEL 0944-73-5952
FAX 0944-73-8403
https://shimama.wixsite.com/shimama2(外部サイトにリンク)
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者