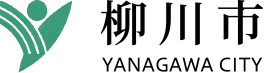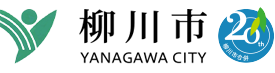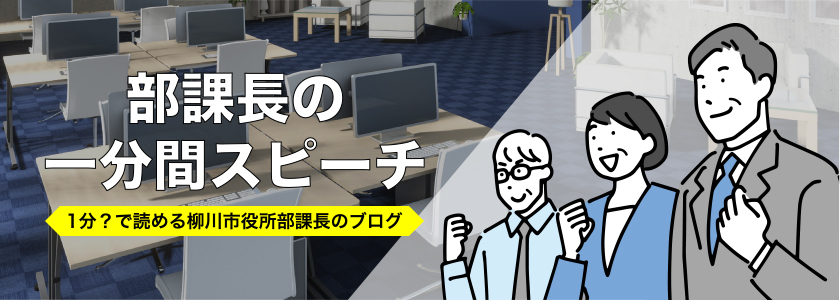皆さんこんにちは。教育部長(併任)三橋庁舎長2年目の武田真治です。よろしくお願いします。
本年度で役職定年なのでこの部課長ブログを書くのもいよいよ最後になりました。
最初にこのブログを書いたのが平成27年の学校教育課長の時でした。
すご~くまじめに今年の教育施策はどうのこうのと書いて企画課に提出したら、当時のO総務部長から電話があり「こげんかつは誰も読まんばい。みんなが興味を持つとば書かんとでけん。書き直し」とおもいっきりダメ出しをされ、全部書き直したのが懐かしい思い出です。
それからはなるだけ面白さを意識して書くようにしたら、たまにブログが面白いと言ってくれる人もいますのでO総務部長のご指導のおかげです。ありがとうございました。
私は教育委員会にいますので学校に行って子どもたちの授業や学級活動を見る機会があります。
今の子どもたちの授業はすごくて小学生でもグループごとに分かれてお互いの意見交換や議論をして新たな考え方に気がついたり、自分の考えをより妥当なものとしたりするような高度な授業をしています。
ある学校では全校集会で小学1年生の児童がはっきりと自分の意見を述べていました。私が子どものころからすると驚くべき進歩です。これからの厳しい時代を生き抜いていくにはこのように主体的に発言できるということは必要な学びだと思います。
皿垣小で行われた「子ども会議」の様子
一方でこれまで私がいいなと思いあこがれる人はみんな「謙虚」な人です。
「謙虚」を辞書で引くと「控え目で、つつましいこと。へりくだって、すなおに相手の意見などを受け入れること。また、そのさま。」とありますが、これまで接してきた先輩たちのなかにもたくさんの謙虚な姿勢を見てきて、そういう人たちといると安心できるし、そういう人にあこがれます。
特にリーダーになる人は「謙虚さ」が必要だと思います。
京セラの稲盛和夫元会長も「常に謙虚であらねばならない。良い雰囲気を保ちながら最も高い能率で職場を運営するためには、常にみんながいるから自分が存在できるという認識のもとに、謙虚な姿勢をもち続けることが大切です。」と言っています。
いまよく言われている「心理的安全性」という状態は、謙虚なリーダーによってつくられると思います。 力を持っているはずの人が謙虚にしていると、関係する職場の人たちはのびのびと仕事できる。のびのびと感じ、のびのびと考え、のびのびと活動できる。すると結果的に生産性があがる。
謙虚が美徳とされてきたのは、そうやって謙虚であることが職場の力を強めることにつながっているからだと思います。
謙虚という言葉で思い出すのが宮沢賢治の「雨ニモマケズ」 です。
雨ニモマケズ風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋ラズ
イツモシヅカニワラツテヰル
(中略)
南ニ死ニサウナ人アレバ
行ツテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクワヤソシヨウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
ヒデリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボウトヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
サウイフモノニ
ワタシハ ナリタイ
なんか読んでるだけでジーンときます。
2011年3月11日の震災後には、この詩句が改めて話題になったそうです。この「行ッテ」という詩句にどれだけ励まされたか、という自衛隊員、医師、ボランティアの人たちが大勢いたそうです。
「雨ニモマケズ」に描かれたような人まではいきませんが
「サウイフモノニワタシハ ナリタイ」
最後の部課長ブログはなんとなく自分の思いだけを書いてしまいました。
それでは皆さんバイなら(斎藤清六風)
次回の部課長ブログは観光課長です。
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者