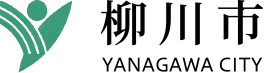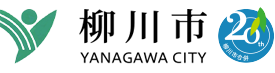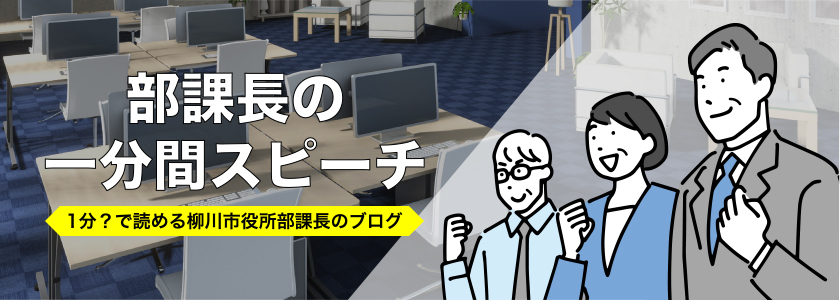皆さんこんにちは。保健福祉部長の池末勇人です。
保健福祉部で2年目を迎え、子どもから高齢者まで全世代の健康や福祉に関する業務を担っていることを日々実感している毎日です。その中で最近の取り組みをご紹介します。
子育て支援課では、今年度、大和地域の6つの小学校が再編により統合されますが、それに合わせて学童保育所も1ヵ所に統合して開設するため、試行錯誤を繰り返し準備を進めてきました。現在は、運営委員会の組織化や支援員の確保など準備が整ってきたところです。今回の統合は1つの学童で150人規模となり、本市では飛び抜けて最大ですし、また学童保育所の教室自体が学校から離れているため、バスで移動するということも初めてとなりますので、支援員の皆さんや運営委員会、保護者の皆さんには、いろんな面でご心配やご迷惑をおかけするかもしれませんが、担当課も精一杯支援していきますので、どうぞよろしくお願いします。
現在、パブリックコメントを終え、最終調整中の「第3期柳川市子ども・子育て支援事業計画」。写真は概要版のサンプルです
それと並行する形で、今年度に計画期間の最終年を迎えている「第2期柳川市子ども・子育て支援事業計画」の見直しを行い、来年度からの第3期計画を策定中です。この計画は、「柳川でよかった! ともにはぐくみ、支える、子育てのまち」を基本理念に掲げ、子どもが生まれてから成長するまでの間、切れ目ない支援を行うために5年ごとに策定している計画書です。時代とともに変化するニーズを的確にとらえるために、今回は支援を受ける当事者である子どもたちやその保護者へのアンケート調査を行い、また、市内で活動する子育て支援団体や関係機関へ聞き取りを行うことで今の課題を洗い出し、それを解決できるような取り組みをどのように行うかを記載した1冊です。
この中で課題として浮かび上がってきたのが、「地域での子育て支援」や、「子どもの発達への不安」、「保護者・家庭への精神的支援」、「各種団体との幅広い連携」などを望む声です。これらの課題をどのようにして解決するのか。すべての課題に対して解決策を持っているわけではありませんし、市役所だけで解決できることも限られています。子育て世代を始め、高齢者の皆さん、地域の皆さん、そして全ての市民の皆さんからご協力いただき、「柳川市に住んでてよかった」「柳川で子育てしてみたい」と思ってもらえるような施策を作っていきたいと思います。
少し前の話ですが、市役所内で行財政改革の職員研修がありました。その時の講師の言葉に「現代のような急激な人口減少は、過去にだれも経験したことがありません。だから、何かやるにしても前例主義は通用しないんです。そんな時代だからこそ思い切ってチャレンジしてください。誰もが成功体験はないんだから、失敗を恐れず、自ら考え抜いて、いろんな取り組みにチャレンジしてください」というような内容だったと思います。この言葉を思い出し、新たな子育て支援策についても前例にとらわれず(公務員は不得意な分野ですが…)チャレンジしていきたいと思います。

このゆびとまれの様子
令和5年4月に利用が始まったむつごろうランドの大型複合遊具
保健福祉部の話題をもう1つ。例年、仕事始め式の中で職員の勤続表彰を行っていましたが、今年は各部で表彰式を行うことになりました。保健福祉部は職員が約80人、会計年度職員を含めると100人以上となるマンモス部。その中で勤続30年の表彰者が2人と少なめでしたが、1月7日の勤務終了後、参加できる人たちに集まってもらい、感謝状の授与を行いました。勤務終了後にわざわざ集まってきてくれるだろうかとか、感謝状を渡すだけで盛り上がるのだろうかとか、私なりに心配していましたが、当日は開始時間には多くの人が集まってくれて、2人の職員の30年という節目をみんなで祝ってくれました。表彰された2人からも、これまでの職員生活を振り返ってのスピーチをいただき、私自身が思いのほか感激して、もう少しで目から汗が落ちそうに。
そこで、せっかくなら集まった人で写真を撮ろうということで(半ば私の独断でしたが…)撮ったのが下の写真です。
2人の表彰者を囲んだ保健福祉部の集合写真。みんないい笑顔です
部内の職員が一緒に写真を撮ることがほとんど無いので、いい機会となりました。みんなが仕事中には見せないようなリラックスした表情にまたホッコリ。日々の仕事で苦労も悩みもあるでしょうが、これだけ大勢の仲間がいることをちょっとだけでも思い出してもらえたらいいなと思いました。
プライベートでのことを1つ。最近の休日の過ごし方で1番多いのは、息子の野球の応援です。応援というと観客席で「がんばれー」や「かっ飛ばせー」というイメージですが、それよりもっと近くでの応援、それはグラウンド内での審判やグラウンド整備のお手伝いです。私は野球経験者ではないんですが(ちなみに中学:サッカー部、高校:陸上部)小学生のころ遊びでやっていたソフトボールの知識を引っ張り出し、それにユーチューブの「少年野球審判講座」なるものを視聴して、行革で学んだ「失敗を恐れずチャレンジしよう」の精神で、練習試合に参加しています。最初は打球の速さにビビったり、アウト・セーフの判断に迷ったりでしたが、息子のプレーを間近で見れるチャンスを逃すまいと、できる限りグラウンドに立ってます。
少し慣れてきた昨年秋ごろの練習試合での話ですが、その日はセカンドの塁審をしていました。相手チームの打者がヒットで1塁を回り、1、2塁間で挟まれた時でした。一瞬何を思ったのか、ショートの息子に対して「早よ、ランナーにタッチせんか」と2塁塁審(私)が大声で叫んだんです。ランナーも野手も息子も、一瞬「えっ!」という表情でこちらを凝視。何より私自身が超びっくり。何でそんなこと言った? でも、プレーは続くので何もなかったかのようにアウトを宣告。スリーアウトとなり、選手は首をかしげながらベンチに戻っていきました。公平なはずの審判が、突然ひとりのお父さんになって我が子を応援するなんてあってはならないことですよね。愛嬌でごまかせる年でもないので、今後は気を付けたいと思います。
その日の夜、息子から「試合中に審判があげんこつ言うたらダメやん。しっかりね」と諭されました。本格的な審判を目指したりはしませんが、中1の息子に負けないようには頑張りたいですね。

練習試合で公平な審判をしている私
次回の部課長ブログは水産振興課長です。
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者