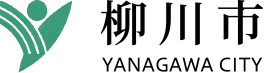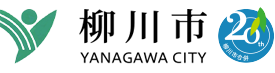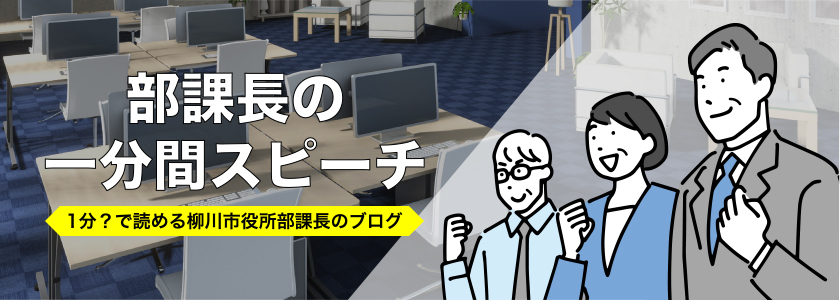皆さん、こんにちは。
三橋庁舎市民サービス課の目野康彦です。
よろしくお願いします。
私は柳川市三橋町木元地区に住んでいますが、今年度、体育委員長という役を担うこととなり、地域の方々が喜んで参加していただけるような地区公民館活動の運営に携わっています。その活動の中に、長年にわたり受け継がれてきた2つの伝統行事がありますので、それを今回ご紹介します。
1つ目は「ぼんでん縄」です。
この行事は、毎年8月15日に行う伝統行事で、100年以上も続いています。
地獄の亡者に大縄をつかませて、せめてお盆の間だけでも救いあげるために行うという一方で、約380年前に筑後地区を襲った大凶作で犠牲になった子どもの霊を慰めるために始まったとも言われています。
私が小学生の頃は、小中学校の男子だけで行っていましたが、子どもの数が少なくなり、このまままでは続けることが難しくなることから、小中学校の生徒児童(男女)のほか、公民館(体育委員)、老人会、子ども会など地域全体で行うやり方に変わってきています。
今年度は、前日の14日に、地区内にある天満宮に、地域の方々が集まり、わらを使って、大人が綱を、子どもたちが鬼のツノに見立てた角や腰みのを作りました。
大人による縄づくり
子どもたちによる角と腰みのづくり
そして、15日早朝、子どもたちが天満宮に集まり、前日に作った角や腰みのを身に付け、手足や服に墨を塗って鬼に変身し、綱をもって、「わっしょい、わっしょい」の元気な掛け声で、地区内を練り歩きました。
地区内を練り歩く子どもたち
福岡県の調査によると、綱を持って地区内を巡行する伝統行事が残っているのは、南筑後地方では、木元地区と隣の起田地区、そしてテレビや新聞で毎年紹介される筑後市久冨地区の3カ所とのことです。
もう1つは「ほんげんぎょう」です。
この行事は、毎年1月に、竹で作ったやぐらに、わらや正月飾りなどを組み、火をつけて、1年間の無病息災などを願う伝統行事です。私が小学生の頃にも、この行事に参加したことがあり、少なくとも50年以上は続いていることになります。
同じような風習は、全国で「さぎちょう」「どんど焼き」などと呼ばれていて、南筑後地方では「ほんげんぎょう」と呼んでいるそうです。
柳川市内の各集落で行われていましたが、伝統に対する意識の変化や、わらが手に入りにくくなったことなどから、実施する集落が減少していましたが、最近では、伝統行事を子どもたちに伝えようと地区ごとに盛んに行われるようになったそうです。
今年は、1月13日に行い、地区内の子どもたちや保護者、地域住民約80人が参加しました。
当日の早朝に、体育委員が、やぐら用の竹を切りに行き、稲の刈り取り跡が残る田んぼに、竹とわらで高さ約6mのやぐらを製作。
やぐら作り
その中に持ち寄ったしめ縄などの正月飾りを入れ、小学校5年生の子どもたちが火入れすると、やぐらは、バチバチという音を立て、瞬く間に燃え上がり、参加者はその炎を見つめ、一年の幸せを祈りました。
勢いよく燃え上がるやぐら
市民サービス課では、毎年、庁舎前の花壇に、ビオラの苗を植栽し、育てています。
ビオラは、花の少なくなる晩秋から春を華やかに彩ってくれる寒さに強いかわいい花です。冬の間は、霜や寒風で縮こまり、枯れてしまったかに見えますが、春を迎えると再び花を咲かせ、こんもりと繁ります。
例年だと11月中旬頃に植栽をするのですが、今年度は温かい日が続いたので、12月中旬に植えました。
厳しい寒さの中、春の訪れを待つビオラたち
ビオラは花が枯れるとすぐに実をつけて種を作ります。種ができるまで枯れた花を放っておくと栄養素を種の生成に使ってしまいます。そこで、新しい花を咲かせるために、咲き終わった花を摘み取ります。これを花がら摘みと言います。
3月には、かわいい子どもたちが、たくさんの花を咲かせ、来庁される方を少しでも癒やしてくれることを願って、北風が冷たい中、週に1回、花がら摘みと水やりを根気よく続けていきたいと思います
 出産・子育て
出産・子育て 高齢者・介護
高齢者・介護 障がい者
障がい者 事業者
事業者